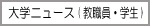到達目標(大学院・専攻別)
本学の大学院は「基礎医学・社会医学・臨床医学あるいはそれらを関連付けた研究に専念し、医学領域の研究・診療・教育・行政における指導者を養成する」と位置付けられている。在学中に習得するべき到達目標を以下に掲げる。
大学院
一般的知識
- ヒト(生物)の構造、機能、病態、および健康と環境ならびに社会との関わりなどについての既知の事項を理解できる。
- ヒト(生物)の構造、機能、病態、および健康と環境ならびに社会との関わりなどについての未知の事項を把握できる。
- 既知および未知の事項について、臓器、細胞、分子レベルで説明できる。
- 自分の研究の重要性・位置づけを認識できる。
- 用いる研究手法の原理・精度・感度などについて理解し説明できる。
- 実験上の規制(RI 、遺伝子組み換えなど)に熟知している。
- 論文のプライオリティー、版権に対する認識がもてる。
- 微生物の一般的取り扱いと処理について熟知している。
- 劇物、毒物、有機溶媒の取り扱いと処理について熟知している。
- 医療廃棄物の取り扱いと処理について熟知している。
- 放射線の種類と人体におよぼす影響について説明できる。
一般的技術
①研究手法
- 目的を把握できる。
- 研究計画を立案できる。
- 適切な手法を用いて、研究を遂行できる。
- 研究上の規則を遵守できる。
- 結果を的確に記録できる。
- 結果を適切に分析、解析できる。
- 結果を論理的にまとめ、結論を導ける。
- 自分の結果を客観的に平易に説明できる。
- 共同研究者と討論できる。
- 研究テーマを設定できる。
②統計・情報
- 種々の統計法を用いて統計処理ができる。
- 必要な情報の収集・交換ができる。
- インターネットを活用できる。
③文献の検索
- 図書館を活用できる。
- 文献検索(二次資料を含む)ができる。
④論文の読み方
- 論文(邦文・英文)の論点を理解できる。
- 論旨を理解し評価できる。
⑤論文の書き方
- 目的・方法・結果・考察の順に簡潔に記載できる。
- 要約としてまとめることができる。
- 図、表などを適切に作成できる。
- 適切な文献を引用することができる。
- 投稿論文に対する査読者の指摘に沿って訂正し、適切な返答をすることができる。
- 英文で書くことができる。
- 印刷原稿の校正ができる(和文・英文)。
⑥学会発表の方法
- スライド、ポスターを作成できる。
- 論旨を明確に述べることができる。
- 質問に対し的確、簡潔な返答ができる。
- 他人の発表を理解し、評価できる。
⑦英語力
- 英語で会話ができる。
- 英語で手紙を書くことができる。
医学教育に関する知識と技術
- 教育原理に関する基本的知識を習得する。
- 教育技法を習得する。
- 教育評価に関する知識と技能を習得する。
一般的態度(意欲、関心を含む)
- 自分の研究に意欲がもてる。
- 最新の研究動向に関心がもてる。
- 自己学習、自己開発を行うことができる。
- 他の研究者と協調し、共同して実験することができる。
- 他の研究者の話を聞き、討論することができる。
- 現時点での自分の能力を知り、適切な専門家の意見をもとめることができる。
- ヒトに関わる社会問題、倫理問題について関心がもてる。
- 研究上の倫理(実験動物の扱い、インフォームドコンセントなど)を遵守できる。
形態学系専攻
知識
a)少なくともこれだけは
- 生体の個体発生、系統発生、先天異常についての基本的概念を理解し説明できる。
- 臓器・組織の形態と機能についての基礎的知識を理解し説明できる。
- 主な疾患の病因、転帰について概説できる。
- 組織標本作製(一般染色、特殊染色、免疫染色 など)の選択とその意義について基本的知識をもち説明できる。
- 通常の光学顕微鏡用標本の作製に関して充分な知識をもてる。
- 必要に応じた免疫組織化学の原理について理解し、説明できる。
- フローサイトメトリーの原理について理解し、説明できる。
- 電顕用試料の作製についてならびにin situ hybridization、充分な知識をもち、説明できる。
- 専門領域の臓器・組織の肉眼、顕微鏡的観察か ら、病態生理について説明できる。
- 病原微生物(細菌、真菌、ウイルス)の基本的知識を述べることができる。
- 腫瘍概念と発生機構に関して理解し説明できる。
- 解剖(解剖学、病理学)例についてその所見を まとめ、報告できる(ただし医師、歯科医師)。
- 遺体の取り扱いについての法律(解剖保存法、 献体法)の知識を述べることができる。
b)できればここまで
- 遺伝子組み換えの原理について理解し、説明できる。
- 専門領域の超微形態の知識について理解し説明できる。
- 細胞間の信号伝達機序を解明するための方法について説明できる。
- 解剖(解剖学、病理学)ができ、その所見をまとめ、報告できる。
技術
a)少なくともこれだけは
- 光学顕微鏡用標本を作製し染色(HE, PAS, Masson 染色や免疫染色など)ができる。
- クリオスタット標本を作製できる。
- 電顕用試料を作製できる。
- 共焦点レーザー顕微鏡を用いた観察ができる。
- 組織より細胞・組織を分離し、培養することができる。
- 消毒・滅菌 操作ならびに無菌操作を実践できる。
- フローサイ トメトリーにより細胞表面および細胞内分子を検出できる。
- 解剖(解剖学、病理学)を行うことができる(但 し医師、歯科医師)。
b)できればここまで
- 特殊な酵素組織化学染色ができる(パラフィン、凍結切片で)。
- 電顕切片を作製し、観察できる。
- 電子顕微鏡観察のための凍結乾燥、凍結割断、 蒸着法などの試料作成ができる。
- フローサイトメーターを用いて、組織から目的をする細胞を回収(ソーティング)できる。
機能学系専攻
知識
a)少なくともこれだけは
- 生体を構成する物質の構造と物理化学的性質について説明できる。
- 生体におけるエネルギーの産生と利用について総合的に説明できる。
- 物質の生体内における代謝過程とその制御機構について説明できる。
- 細胞固有の生理的機能について説明できる。
- 細胞の増殖、分化、死を制御する因子を挙げ、作用を説明できる。
- 細胞を構成する物質を挙げ、機能と関連づけることができる。
- 生体における恒常性を制御理論の上で論じ、いくつかの例を挙げて解説することができる。
- 刺激、刺激応答、信号伝達、反応を広く論ずることができる。
- 受容体、経膜的信号伝達、細胞内情報伝達の分子機構について説明できる。
- 生体の防御反応、免疫システムについて説明できる。
- 生体と薬物の相互作用について系統的に説明できる。
- 放射線の種類、性状を理解し、生体に及ぼす作用について説明できる。
- 遺伝について、遺伝子レベルから個体レベルまで説明できる。
- 遺伝子工学の利用、応用について説明できる。
b)できればここまで
- 遺伝子組み換えの原理について説明できる。
- 種々の電気的記録法の原理について説明できる。
- 細胞間の信号伝達機序を解明するための方法について説明できる。
技術
a)少なくともこれだけは
- 自分の扱う物質の定性分析ができる。
- 自分の扱う物質の定量測定ができる。
- 分光光度計による測定ができる。
- 光学機器による観察ができる。
- 蛋白質の定量測定ができる。
- 単一細胞の応答を記録し、分析できる。
- 細菌培養ができる。
- 動物の飼育、麻酔、必要な手術、安楽死の手技、屍体処理が適切にできる。
- 自分用の特殊な実験装置を工夫して作成することができる。
b)できればここまで
- PCR を用いて遺伝子を増幅できる。
- ゲノム・遺伝子データベースの使用ができる。
- 遺伝子をクローニングしてその構造を解析することができる。
- 顕微鏡下でのマイクロマニピュレーションができる。
- レーザー顕微鏡を用いた観察ができる。
社会医学系専攻
知識
a)少なくともこれだけは
- 疫学の概念と方法について説明できる。
- 疫学で用いられるデータ解析の方法について説明できる。
- 統計学の基本概念と方法について説明できる。
- 実験データの解析方法について説明できる。
- 世界保健機関、ユニセフ等の国連機関の活動およびわが国の援助のあり方について説明できる。
- 環境汚染の 発生要因と健康影響について説明できる。
- 有害物質の 吸収、分布、代謝、排泄について説明できる。
- 職業性疾病 の原因、予防、診断、治療について説明できる。
- 死の判定と法的取り扱いについて説明できる。
- 異状死体とは何かを理解し、例を挙げて説明できる。
- 法律によって医師に課せられている義務について説明できる。
- 外因死と内因死の法医学的問題について説明できる。
- 医療事故とその法的対応について説明できる。
b)できればここまで
- 臨床疫学における生存分析について説明できる。
- 分析疫学の内容と利用法について説明できる。
- 臨床試験の方法について説明できる。
- 実験計画法の概念と方法について説明できる。
- 臨床活動の科学的評価ができる。
- 開発途上国の子供の主要死因について説明できる。
- 急性呼吸器感染症、および下痢症対策の概略について説明できる。
- 世界の予防接種状況について説明できる。
- 家族計画、リプロダクティブ・ヘルスについて概念を説明できる。
- エイズの疫学状況とコントロールについて説明できる。
- 地球の温暖化と大気汚染、森林破壊について説明できる。
- 開発途上国の経済問題と保健との関わりについて説明できる。
- 政府開発援助の種類と特徴について説明できる。
- 遺伝子分析を用いた疫学的手法について説明できる。
- 主要な感染症の予防法について説明できる。
- 環境汚染の 評価と対策について説明できる。
- 労働衛生の 現況と対策について説明できる。
- 産業医の業務と労働衛生管理について説明できる。
- 突然死の診断と予防について説明できる(法医学領域)。
- 創傷に関する法医学的診断事項を列挙し、説明できる(法医学領域)。
- 犯罪被害者の法医学的対応について説明できる (法医学領域)。
- 濫用薬物の人体に及ぼす影響を述べ、分析結果を評価できる(法医学領域)。
- DNA多型による個人識別について説明できる (法医学領域)。
- 事故と賠償医学上の問題について説明できる (法医学領域)。
- 鑑定書について説明できる(法医学領域)。
技術
a)少なくともこれだけは
- インターネット、文献検索システム等を活用して、研究の実施、評価に必要な情報を収集できる。
- 臨床統計等で汎用される基本的な統計処理を統計パッケージ等を使用して計算ができる。
- 主要な熱帯感染症に関する情報の収集と分析ができる。
- 化学物質の毒性評価に関わる基本的実験ができる。
- 死体検案の概要を知り、実施できる(法医学領域)。
- 死亡診断書(死体検案書)・死産証書(死胎検案書)を作成できる(法医学領域)。
b)できればここまで
- 統計パッケージ等を用いて臨床データの生存解析ができる。
- 無作為割付等の手法を使って臨床試験等の研究計画を等定できる。
- 分析疫学データの基本解析、多変異解析ができる。
- 開発途上国における地域での保健サーベイを企画・実施・分析できる。
- 主要な熱帯感染症の病原体標本の作製、同定ができる。
- 環境毒性学に関わる実験を企画・実施・報告することができる。
- 法医解剖の補助ができる(法医学領域)。
- 法医解剖に伴う各種検査の方法を習得し、実施できる(法医学領域)。
- 鑑定書の書き方を習得し、作成できる(法医学領域)。
- 他者の学習を支援できる。
- 他者に適切に教えることができる。
内科系専攻
知識
a)少なくともこれだけは
- 各臓器の形態・機能・病態とそれらの相関を評価できる。
- 細胞・組織の微細構造と分泌機能・受容体機 能・細胞内情報伝達機構を理解し、相互作用と恒常性維持機構について説明できる。
- 細胞・組織の増殖・分化・死について、それら の誘導の機序と経過を述べることができる。
- 代表的疾患の病因・発症機序と生体防御機能について説明できる。
- 精神心理状態、人格、性格の評価法について説明できる。
- 一般的症状の鑑別ができる。
- 各種画像診断法の原理について説明し、結果を解釈できる。
- 合理的治療方針の立て方について述べることができる。
- 臨床薬理学の基本を理解し、病態機序との関連で薬物療法について説明できる。
- 臨床統計の手法を理解し、適正な適用と結果の評価ができる。
b)できればここまで
- 各臓器の形態・機能・病態の、発達・加齢による変化について説明できる。
- 主な腫瘍のTNM分類について説明できる。
- 精神心理状態の加齢に伴う変化について説明できる。
- 専攻する分野の認定医又は専門医になるために必要な知識を説明できる。
- 遺伝子工学の基本的原理について説明できる。
技術
a)少なくともこれだけは
- 一般的検査の所見を解釈し、診断に利用できる。
- 汎用される画像診断法の読影ができる。
- 核医学の原理を理解し、診療・研究に応用できる。
- 病態機序を把握し、心理的社会的背景を考えて診察できる。
- 精神心理学的評価尺度を利用して適切に評価できる。
- 基本的診察技法、特に心肺蘇生法、救急処置 法、栄養法を適正に実践できる。
- 臨床判断学の手法に習熟し、論理的に適切な診察を実践できる。
- 担当する症例について問題を抽出整理し、診断・治療・予後観察について必要な情報を適正に収集できる。
- 一般的統計手法を習得し、臨床統計及び実験研究に適正に応用できる。
- 症例報告論文をまとめることができる。
- 新しい診察法開発と適用のプロセスを理解し、 科学的論理的根拠を整えることができる。
- 対立する意見を理解し、論理的に対応することができる。
b)できればここまで
- 各臓器の微細構造の正常と異常を区別できる。
- 専攻する分野の認定医または指定医になるために必要な技術を修得できる。
- 分子生物学、細胞生物学の基本的技術を修得し、遺伝子機構を病態の解明に応用できる。
- 倫理的、生物科学的、諸事項を考慮して臨床研究を企画し、プロトコールを作成し進めることができる。
外科系専攻
知識
a)少なくともこれだけは
- 外科系領域の重要疾患の概念病態について、理解し説明できる。
- 専門領域の重要疾患と全身疾患との関係について説明できる。
- 滅菌消毒の概念および感染予防について、充分な知識をもつことができる。
- 基本的外科的処置と手術手技について、理解し説明できる。
- 外科的侵襲と生体反応について、理解し説明できる。
- 専門分野における外科的疾患の手術適応について説明できる。
- 炎症のメカニズムについて、説明できる。
- ショックの機序・病態知見・病理・薬理について、説明できる。
- 臓器移植に関する基礎的知識を説明できる。
- 創傷治療機転を組織レベル・細胞レベル・分子レベルで説明できる。
- 臨床例の症例報告ができる。
b)できればここまで
- 専門領域に関する組織の微細胞構造について、 説明できる。
- 臨床腫瘍学について基礎から臨床までの知識を もつことができる。
- 血液浄化法の概略について理解し、その種類と 原理を説明できる。
- 専門領域における必要な法的知識を把握できる。
- 免疫系の認識機構について説明できる。
技術
a)少なくともこれだけは
- 専門領域における重要疾患の外科的手技と、術前術後の管理ができる。
- 外科的診断法を理解し、なかでも内視鏡・超音波・X線検査の技術を用いて診断することができる。
- 専門領域における各種のカテーテル管理ができる。
- 救急患者や外傷患者の救急処置を行うことができる。
- 止血法と輸血管理ができる。
- 心肺蘇生の原理を熟知し、施行できる。
- 動物実験での麻酔管理を確実に実施できる。
- 外科的実験手法の安全管理を理解し対応できる。
- 急性実験・慢性実験の違いを恒常性を基準に評価できる。
- 動物実験のモラルと社会認識を理解し、対応できる。
b)できればここまで
- 合併症を伴う患者の手術、術前術後の管理ができる。
- 少なくとも1つでも先端技術の開発に参加し、 基礎技術を修得することができる。
- 専門領域に関する問題について、知識を整理し英語で討論できる。
先端生命医科学系専攻
知識
a)少なくともこれだけは
- バイオメディカルエンジニアリングの全体像を 理解し、説明できる。
- 手術の低侵襲化に対する社会的背景、具体的な方法に関して例を挙げて説明できる。
- 手術中にモニタするバイタルサインや手術前後に撮影する画像などの生体情報を説明できる。
- 画像処理技術(3次元再構成、マーカによるレジストレーションなど)の手術への応用に関して説明できる。
- ニーズと必要技術を明確にして実用的なシステム開発を行う方法論を説明できる。
- 染色体、ゲノム、遺伝子、核酸の構造、機能の分子生物学的、医学的意味を説明できる。
- 単一遺伝子疾患、ミトコンドリア異常、多因子疾患の遺伝について説明できる。
- 遺伝子診断、遺伝子治療の方法と意義を説明できる。
- 遺伝子変異、遺伝子多様性(多型)について説明できる。
- 遺伝の法則と集団遺伝学を理解し、連鎖や連鎖不平衡の概念を説明できる。
- 各種の遺伝統計学的手法の概念や応用法の違いを説明できる。
- ゲノム解析に必要な統計学を理解し、検定、推定、最尤法の概念を説明できる。
- 薬理遺伝学、薬理ゲノム学の理論、個別化医療 について説明できる。
- 遺伝医学における倫理問題について説明できる。
- 移植抗原、組織適合性、HLA抗原など移植免疫に関する基礎知識を理解し説明できる。
- 免疫機構を理解し、拒絶を抑えるための免疫抑制、免疫寛容などの基礎について説明できる。
- 移植臓器の虚血障害など、臓器保存に関する基礎知識を習得する。また具体的な保存法について説明できる。
- 体外循環に関連した、医用流体力学についての基礎知識を説明できる。
- 人工臓器の性能と設計に関わる装置工学的基礎知識を説明できる。
- 生体と接触し用いられる人工臓器を構成するバイオマテリアルの基礎について、理解し説明できる。
- ドラッグデリバリーシステムDDSの概念について理解し、説明できる。
- バイオマテリアル・人工臓器が生体と接触したときの生体反応について、理解し説明できる。
- バイオマテリアルとしての高分子材料の合成法とその解析法について、理解し説明できる。
- 各臓器・組織における組織工学について理解し説明できる。
- サイトカインネットワーク、細胞周期、増殖、分化について理解し説明できる。
- 人工心臓、人工肺などの循環系人工臓器の原理、構造、機能、特徴について、理解し説明できる。
- 人工腎臓、人工肝臓などの代謝系人工臓器の原理、構造、機能、特徴について、理解し説明できる。
- 微細加工技術に関する技術の特徴を理解し、説明できる。
b)できればここまで
- 集学的アプローチで新しい研究の提案ができる。
- 手術支援ロボティクスの概念と現状を説明できる。
- 医療情報ネットワークの概念と医用画像規格 (DICOM)を説明できる。
- 各種連鎖解析の理論を正確に理解し、駆使することができる。
- 分子進化学を理解し、系統樹を書くプログラムの概念を説明できる。
- 移植情報の集積と分析ならびに臨床への情報提供法等について理解し説明できる。
- 組織・臓器の利用に関する法規制と社会倫理について理解し、正しく説明することができる。
- 各臓器移植に関して、臓器保存法、臓器移植術、免疫抑制法、拒絶反応、合併症、人工臓器との関連などについて理解し、説明できる。
- 組織移植と細胞移植に関して、組織・細胞採取、保存法、組織/細胞移植術、拒絶反応、合併症などについて理解し、説明できる。
- 体外免疫調節としての人工臓器の役割について説明できる。
技術
a)少なくともこれだけは
- バイタルサインや医用画像をファントム対象に 計測することができる。
- 医用画像を画像処理ソフトウェアに入力して、 3次元再構成することができる。
- 機械工作の基礎を理解し、手術に必要な部材を 設計・製作することができる。
- 小さな家系図からパラメトリック連鎖解析を手計算でできる。
- 大きな家系図のデータをコンピュータに入力 し、連鎖解析のソフトウェアを使うことができる。
- インターネット上で塩基配列や地図情報を検索でき、個人のものとして分析できる。
- 既に原因のわかっている疾患について、SNPsデータからその原因遺伝子座を検索し確定できる。
- HLAタイピングなど移植免疫に関連した基礎 技術を実践できる。
- 具体的な臓器保存に関する基礎技術を習得し、実践できる。
- 人工臓器とそれを構成する要素(回路など)の組立ならびに操作を行うことができる。
- 人工臓器の性能評価実験を行うことができ、性能に及ぼす各種因子の影響を正しく評価できる。
- バイオマテリアルとしての高分子材料の合成手法について習熟し、実験を行うことができる。
- 種々の分析機器を用いて高分子材料の特性解析を行うことができる。
- 移植免疫に関連した基礎技術について習熟し、実験を行うことができる。
- 人工臓器の組立、操作、性能評価について習熟し、実験を行うことができる。
- 動物実験のモラルと社会認識を理解し、対応できる。
- 組織から細胞を採取・分離・培養ができる。
- 高分子DNAを抽出できる。
- 遺伝子配列の解析、遺伝子導入ができる。
- 薬物、遺伝子投与の最適化の意味とその方法を 知り、その手法を説明できる。
b)できればここまで
- 3次元画像処理(立体構成、レジストレーション)のアルゴリズムを理解し、必要に応じて改良することができる。
- 手術支援ロボティクスに必要なメカトロニクス の基礎を理解し、モータ制御などの電子回路を設計・製作することができる。
- Unixのコマンドを使い、連鎖解析のアプリ ケーションを使うための方法を理解し説明できる。
- 生体組織、臓器を模倣した各種細胞のパターニング手法を理解し、様々の機器を利用し細胞のパターニングを行うことができる。
- 再生医療研究に関するグローバル的な動向、流れを把握、理解し説明ができる。