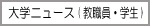先端工学外科学分野
概要
本研究室では、AIやロボティクスなどの先端技術を活用し、高度な医療の実現を目指した研究開発を行っています。特にインテリジェント手術室を中心とした情報誘導手術の研究では、術中MRIやOCT、光線力学診断、機能検査など多様なモダリティを統合し、手術の質向上を図っています。また、各診療科と連携した手術支援ロボットや治療デバイス、AIによる臨床予測、遠隔支援なども推進し、モバイルSCOTや在宅医療ロボットの社会実装にも取り組んでいます。さらに、医療機器レギュラトリーサイエンスにも注力し、基礎から臨床・製品化までの一貫した体制で、広い視野を持つ人材育成を行っています。


研究可能テーマ
他科との共同臨床試験・研究等
・外科治療における手術戦略システム(スマート治療室の展開)
・スマート治療室が病院の新しい概念を創る モバイルSCOT
・外科手術支援ロボット・デバイスの研究開発
・術中言語機能検査のAI解析を通じ取り組むリスク評価と患者安全
・テクノロジーを用いた患者・市民参画(PPI)研究への取り組み
・手術室のデジタルツイン化の基盤技術 スマート治療室の開発
・医療機器におけるレギュラトリーサイエンス
以上、大学院生とテーマを共同作成した臨床研究を含め、様々な医療分野における課題について数多く実施中である。
・外科治療における手術戦略システム(スマート治療室の展開)
・スマート治療室が病院の新しい概念を創る モバイルSCOT
・外科手術支援ロボット・デバイスの研究開発
・術中言語機能検査のAI解析を通じ取り組むリスク評価と患者安全
・テクノロジーを用いた患者・市民参画(PPI)研究への取り組み
・手術室のデジタルツイン化の基盤技術 スマート治療室の開発
・医療機器におけるレギュラトリーサイエンス
以上、大学院生とテーマを共同作成した臨床研究を含め、様々な医療分野における課題について数多く実施中である。
スタッフ紹介
.jpg) 教授 正宗 賢
教授 正宗 賢 准教授 田村 学、北原 秀治、飯塚 幸恵(兼務)
講師 吉光 喜太郎、石川 達也(兼務)、稲野辺 奈緒子(兼務)
助教 冨永 絢子(兼務)、原 伸太郎(兼務)