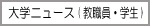腎臓内科学分野
概要
私どもの診療のポリシーは「患者さんを中心に考える」ということです。
腎臓病は短期決戦ではなく、長期に病気と戦う患者さんに寄り添っていくことになります。病気だけをみて診療することなく、患者さんの気持ちや社会生活なども尊重して治療することをモットーとしています。
腎臓内科学分野は、1973(昭和48)年1月に初代主任教授である杉野信博先生が、東京女子医科大学総合内科教授として着任し、腎臓内科の診療・研究にあたられたことに始まります。
1979(昭和54)年4月に、腎臓病総合医療センターが設立され、腎臓内科が診療科としてスタートしました。
1983(昭和58)年7月には、第四内科学講座が開講し、杉野信博教授が初代主任教授に就任されました。
1992(平成4)年4月からは二瓶宏先生が二代目主任教授に就任されました。
2005(平成17)年4月からは新田孝作先生が三代目主任教授に就任されました。
2018(平成30)年に、腎臓内科学講座と改名されました。
現在では星野純一教授・基幹分野長を中心に、総勢約90名の医局員で構成されています。これだけの人数の腎臓内科医で構成されている医局は、国内外でも数少ないと自負しております。 医局同窓会登録人数も300名を超え、関連病院や地域中核病院として、研修医の指導および患者様の受け入れに、ご協力いただいております。医局の同窓会との連携も密で、年に1回の総会を開催して、情報交換をしています。
教育内容
患者さん中心の医療を推進していくことを基本理念としております。そのため臨床医師としての基本的で最も大切な姿勢、態度、技能を修得することが目標です。
後期研修医(医療練士)の研修内容は新内科専門医制度のカリキュラムに則り、腎臓病のみならず一般内科臨床の経験を積み、専門医(内科、透析、腎臓)、学位の取得を目指します。当科の関連病院は全て高度医療を行う総合病院であり、指導医はOB・OGです。帰局後は大学病院にて腎臓病の臨床をさらに深めると共に、研究(基礎、臨床)に着手し学位論文を仕上げることを目標にしています。研究を重点的に行う場合には大学院への進学や、当科の垣根を取り払いTWIns、総合研究所での研究、あるいは国内留学、国外留学も可能です。腎臓病総合医療センターの特徴を生かし、上級研修については腎臓小児科、泌尿器科、腎外科(移植医療)へのローテーションも行っております。
研究内容
当科では創設時より臨床を重視しており、臨床から生じた疑問を研究し臨床に還元することを目標にしております。学位研究はそれを取得するのが医師としての出発点と考えて後期研修医も研究に尽力しております。当科の豊富な臨床データや病理標本を基に行う臨床研究、さらに病態を深めるために実験動物モデル、遺伝子研究、再生医療などの基礎研究も行っています。
代表的な臨床研究
①腎炎、ネフローゼ症候群:腎炎・ネフローゼ症候群に対するリツキシマブ治療研究、IgA腎症の治療や予後に関する研究、ループス腎炎・血管炎などの二次性糸球体腎炎に関する治療や予後に関する研究
②慢性腎臓病研究:慢性腎臓病患者の貧血治療や血管石灰化に関する検討
③
多発性嚢胞腎(ADPKD):トルバプタン治療、嚢胞感染症治療、遺伝子研究、脳動脈瘤研究
④透析関連:腎臓内科と血液浄化療法科のメンバーが関与し、透析療法の臨床症例、病態生理の検討を行っている
⑤腎臓リハビリテーション、栄養学
スタッフ紹介

- 教授・基幹分野長
-
星野 純一
- 専門領域
- 腎臓内科学
膠原病
多発性嚢胞腎
糖尿病性腎症
腎臓リハビリテーション
臨床疫学

- 客員教授
-
土谷 健
- 専門領域
- 水・電解質
代謝異常
尿細管間質障害
多発性嚢胞腎
透析療法
貧血

- 客員教授
-
新田 孝作
- 専門領域
- 慢性腎臓病
急性腎障害
腎炎
ネフローゼ症候群
透析療法
血管石灰化

- 客員教授
-
内田 啓子
- 専門領域
- 腎炎
ネフローゼ症候群
膠原病・血管炎に
伴う腎疾患(とくにループス腎炎)
生体腎移植
ドナー評価

- (兼務)准教授
-
海上 耕平
- 専門領域
- 腎移植(移植免疫、移植後合併症、腎生検など)
臓器移植(ドナー提供、移植内科医育成など)

- 講師
-
片岡 浩史
- 専門領域
- 腎臓病一般
腎炎
肥満腎症
多発性嚢胞腎

- 講師
-
眞部 俊
- 専門領域
- 腎炎
ネフローゼ症候群
腎病理
遺伝性腎疾患
多発性嚢胞腎
大学院
医学研究科内科系専攻腎臓内科学分野ホームページ
当分野では大学院生の受け入れを行っています。研究可能なテーマは、①慢性腎臓病に関する臨床研究、②透析患者の合併症・特に心血管合併症に関する研究、③尿細管・間質障害にかかわる分子に関する研究、④腎炎の発症と進展に関する機序に関する研究、⑤遺伝性腎疾患の新たな原因遺伝子の探求に関する研究です。研究に関しては、TWIns、基礎系教室、理化学研究所、他大学の研究室とも連携してテーマに即した研究環境を提供しています。