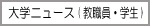微生物学免疫学分野
概要
私たち微生物学・免疫学教室では、微生物の構造、遺伝子といった基礎的な微生物学の研究から、微生物に対する免疫機構を解明する免疫学の研究まで、多様な領域に取り組んでいる。特に当教室は、細菌の遺伝子改変技術や細菌叢(microbiota)解析において高度な技術を有しており、これらを活用した研究を推進している。本教室は、大学病院の臨床医との密接な連携のもと、病原体がどのようにして炎症や疾患を引き起こすのかを分子レベルで明らかにしようとする基礎研究を行っている。これまで原因不明とされてきた疾患に、実は細菌が関与している可能性を見出すなど、新たな病因の解明にも挑戦している。さらに近年では、代謝系が脂肪組織や免疫細胞の働きに与える影響に注目し、それらがさまざまな疾患の発症や経過にどのように関与するかについての研究も進めている。炎症や免疫の関与が疑われる多様な疾患に対する微生物学的な基礎的アプローチに関心を持ち、臨床と基礎をつなぐ研究に従事することを希望する者にとって、有意義な研究環境を提供している。
研究可能テーマ
(1)細菌―宿主相互作用の分子機構解析
Staphylococcus aureus、Streptococcus spp.、Escherichia coli、Burkholderia spp.の細菌構造と遺伝子および細菌の免疫回避機構について分子生物学的に探求する。
(2)生体細菌叢の解析
細菌叢の網羅的解析を各種マウス疾患モデルや各種疾患の臨床検体を用いて行い、細菌叢の偏向と疾患の関与を検討する。腸管を中心とした粘膜のリンパ組織の細胞構成を解析し疾患発症との関連を調べる。原因不明の疾患(免疫関連疾患など)の発症機序が研究の対象となる。
(3)自己免疫疾患の発症機序の解析
感染による免疫寛容の破綻機構について実験動物モデルを用いて探求し、自己免疫疾患の病態を解明する。
(4)代謝性疾患における免疫担当細胞の解析
2型糖尿病や肥満に起因する代謝障害の病態と脂肪組織の関係について、マウスおよび培養細胞を用いて解析する。本研究は治療薬および食品成分を使用し、生活習慣病の治療・予防法の探索を目指す。
(5)実験用動物の新規病原体の病原性ならびに感染症病態の解析
新たに分類され、実験用動物の感染症の原因となる可能性のある細菌について解析し、新規病原性細菌として提案する。
Staphylococcus aureus、Streptococcus spp.、Escherichia coli、Burkholderia spp.の細菌構造と遺伝子および細菌の免疫回避機構について分子生物学的に探求する。
(2)生体細菌叢の解析
細菌叢の網羅的解析を各種マウス疾患モデルや各種疾患の臨床検体を用いて行い、細菌叢の偏向と疾患の関与を検討する。腸管を中心とした粘膜のリンパ組織の細胞構成を解析し疾患発症との関連を調べる。原因不明の疾患(免疫関連疾患など)の発症機序が研究の対象となる。
(3)自己免疫疾患の発症機序の解析
感染による免疫寛容の破綻機構について実験動物モデルを用いて探求し、自己免疫疾患の病態を解明する。
(4)代謝性疾患における免疫担当細胞の解析
2型糖尿病や肥満に起因する代謝障害の病態と脂肪組織の関係について、マウスおよび培養細胞を用いて解析する。本研究は治療薬および食品成分を使用し、生活習慣病の治療・予防法の探索を目指す。
(5)実験用動物の新規病原体の病原性ならびに感染症病態の解析
新たに分類され、実験用動物の感染症の原因となる可能性のある細菌について解析し、新規病原性細菌として提案する。
スタッフ紹介
教授・基幹分野長 柳沢 直子
准教授 大坂 利文
助教 上芝 秀博
助教 飯塚 讓
助教 西田 隆司
准教授 大坂 利文
助教 上芝 秀博
助教 飯塚 讓
助教 西田 隆司