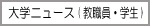顕微解剖学・形態形成学分野
概要
本分野では形態学、細胞生物学の基本・最先端の技術を用いながら、組織の根底となる組織幹細胞生物学を中心に学習し、組織構造と形成をMedical Biologyの観点から学んでいきます。また、Scienceの共通語である英語を用いて、read, write, discuss and present your science in Englishを達成できるように努め、臨床医学のBackboneである基礎医学研究を学び、将来、scientist/clinician scientistとして世界に発信できる人材育成を行っていきます。
研究可能テーマ
(1)骨髄造血幹細胞(hematopoietic stem cell;HSC)の内因性制御機構の解析
造血幹細胞の内因性制御機構としてCytokine signal, cell cycle regulation, mitochondria metabolism, oxidative stress, iron metabolismなどがどのようにHSCの自己複製・分化・維持のCell fateを決定するのかを解析する。胎生期、新生児期、成人期、老年期の造血解析。
(2)造血幹細胞(hematopoietic stem cell;HSC)の骨髄ニッチによる外因性制御機構の解析
HSCの微細環境である骨髄ニッチ(mesenchymal stem cell, endothelial cell, osteoblastなど)によるHSC制御機構の解析を行う。
(3)DNA損傷修復因子の造血幹細胞における機能の解析
DNA損傷修復因子のなかでも架橋修復因子であるファンコニ貧血分子に着目して、造血幹細胞の発生、成熟、老化との関わりを生物学的、分子生物学的手法を用いて解析する。
(4)消化管ペースメーカー(カハールの介在細胞)の形態と機能
カハールの介在細胞(Interstitial cells of Cajal;ICC)は、消化管運動におけるペースメーカーあるいは興奮伝達機構として働くことが知られている。そこで、種々の実験動物や疾患モデル動物を用いて、消化管の特定の部位ごとにICCがどのような細胞性ネットワークを形成し運動制御に関わっているかを形態学の立場から解明を試みる。
その他にも分野を問わず、組織幹細胞学、形態学の解析が可能です。幹細胞解析においては、主に、Flow Cytometry, ICC, IHC, transplantation, cell culture などの手法を用いた解析が可能です。形態学解析においては光学顕微鏡、共焦点レーザー顕微鏡、電子顕微鏡などを用いた形態計測、画像解析が可能です。
造血幹細胞の内因性制御機構としてCytokine signal, cell cycle regulation, mitochondria metabolism, oxidative stress, iron metabolismなどがどのようにHSCの自己複製・分化・維持のCell fateを決定するのかを解析する。胎生期、新生児期、成人期、老年期の造血解析。
(2)造血幹細胞(hematopoietic stem cell;HSC)の骨髄ニッチによる外因性制御機構の解析
HSCの微細環境である骨髄ニッチ(mesenchymal stem cell, endothelial cell, osteoblastなど)によるHSC制御機構の解析を行う。
(3)DNA損傷修復因子の造血幹細胞における機能の解析
DNA損傷修復因子のなかでも架橋修復因子であるファンコニ貧血分子に着目して、造血幹細胞の発生、成熟、老化との関わりを生物学的、分子生物学的手法を用いて解析する。
(4)消化管ペースメーカー(カハールの介在細胞)の形態と機能
カハールの介在細胞(Interstitial cells of Cajal;ICC)は、消化管運動におけるペースメーカーあるいは興奮伝達機構として働くことが知られている。そこで、種々の実験動物や疾患モデル動物を用いて、消化管の特定の部位ごとにICCがどのような細胞性ネットワークを形成し運動制御に関わっているかを形態学の立場から解明を試みる。
その他にも分野を問わず、組織幹細胞学、形態学の解析が可能です。幹細胞解析においては、主に、Flow Cytometry, ICC, IHC, transplantation, cell culture などの手法を用いた解析が可能です。形態学解析においては光学顕微鏡、共焦点レーザー顕微鏡、電子顕微鏡などを用いた形態計測、画像解析が可能です。
スタッフ紹介
教授・基幹分野長 石津 綾子(東京女子医大院2009年卒)
准教授 横溝 智雅(京都大学大学院医学研究科2001年卒)
准教授 横溝 智雅(京都大学大学院医学研究科2001年卒)