ピックアップ
2017年06月01日看護学部臨床看護実習
プロフェッショナルをめざす強い意志が芽生える
2014年1月から2月にかけての約2週間、東京女子医科大学病院の病棟では、真新しい看護ユニフォームに身を包んだ初々しい女性たちがきびきびと動き回っていた。
■根拠に基づいた看護を実践
看護は、患者さんの疾病からの回復 と健康の維持・増進を図り、質の高い生活ができるよう支援する活動である。そ して、看護を支える知識や技術の基盤 となる“実践の科学”が看護学であり、それを学ぶ過程において実際に臨床の 場で行う実習は、欠くことのできない重要なものである。
女子医大看護学部では、1年生がより良い人間関係の構築を大切にした基礎看護学実習を行うのに続き、2年生と 3年生には成人看護学実習がカリキュラムに組まれ、さらに各専門領域での実習が行われる。
2年生の成人看護学実習Ⅰは、患者さんとの人間関係づくりをベースに、看護理論を用いて「根拠に基づいた看護の実践」に取り組む。3年生の成人看護学実習Ⅱでも、実習Ⅰと同様に看護計画を立案し、それを実践し評価するという一連のプロセスを4週間かけてしっかりと学ぶ。いずれも、1人の学生が1人の患者さんを受け持ちながら看護を実践していく。
女子医大病院の病棟で動き回っていた初々しい女性たちは、この成人看護学実習Ⅰを学んでいた看護学部の2年生たちである。彼女たちは少人数のグループに分かれ、中央病棟、西病棟A・B、第1病棟の各病棟に分散し、消化器外科や呼吸器外科、循環器内科、脳神経外科、化学療法緩和ケア科などの診療科を舞台に病棟実習を行った。このうち、西病棟Bの5階にある脳神経外科で学んだ5人グループの実習の様子を追ってみよう。
■ピュアな気持ちで実習に臨む
病棟実習の初日、まず脳神経外科病棟の大熊あとよ看護師長の挨拶があった。 「脳神経外科病棟に入院されているのは、 ほとんど脳腫瘍の患者さんです。中には意識障害がある患者さんもいますので、 コミュニケーションをうまく取れないことも あるでしょう。大事なことは、患者さんの表情をよく観察することです」と、脳神経外科病棟の特性を説明。
また、「患者さんは40~50歳代の人が多く、みなさんを自分の家族のように思っていろいろな話をされると思います。 その中から、患者さんの生きた情報をつかみ取ってください」 と要望。さらに、「私たちは“患者さんに選ばれる病棟づくり” をしていますが、同時に“学生に選ばれる病棟づくり”もめざしています。ですから、ピュアな気持ちで病棟実習に臨み、気がついたことはどんどん提案してください」 と語った。
このあと5人の学生はそれぞれ受け持つことになった患者さんの病室を訪れ、自己紹介。そして、患者さんの情報収集に努めた。K.K.さんが受け持った患者さんは、元気そうに見えるものの余命が短い。それを聞いたK.K.さんはショックを受け、他の4人も驚きを隠せず、命の重みを考えさせられる重々しい気分でのスタートとなった。
■ケアプランを中止する判断も重要
脳神経外科病棟実習は午前8時半から始まる。前日の実習記録と当日の学習目標・看護計画を、朝のカンファレンスで教員に報告。ケアプランの修正などの指 導を受けた後、受け持つ患者さんの担当看護師と調整し、タイムスケジュールや具体的な看護方法についてアドバイスを受け、患者さんへのケアを実行する。
そして午後2時以降、その日に実施し たこと・学んだことを看護師に報告し、3時に病棟から学部校舎へ移動して学内カンファレンスを行う。こうして8日間、実習が続く。
脳神経外科病棟で実習に臨んだ5人 は、日が経つにつれて当初の重々しい気分から抜け出し、はつらつとケアに取り組むようになった。5日目朝のカンファレンスの一端を紹介しよう。
K.M. バイタルサイン (体温、血圧、脈拍、呼吸などの情報)を取りにいったら、患者さんがつらそうに眠っていました。どうしようかと考えましたが、声をおかけしてバイタルサインを取ることにしました。また、少しけいれんを起こされていましたが、それは不安な気持ちからでした。
教員 患者さんの具合が悪そうだったので、バイタルサインを取らなかったというケースがありました。素人ならそっとしておいてあげようと思うかもしれませんが、具合が悪そうだからこそバイタルサインを取らなければなりません。患者さんの状態を把握するためにバイタルサインを取ったことは適切な判断でした。患者さ んの気持ちも引き出せてよかったですね。
K.K. 患者さんは午前中から微熱があり、「首が痛い」とおっしゃったので、体温を測ることを優先させ、予定していた足浴プランの実行を中止しました。 その後、体温はさらに上昇しました。 このことから、患者さんにはそのときに必要なケアを行うことが最善の策だと思い ました。
教員 患者さんは翌日、「私の熱が上がることをKさんが予測したんですよ」 と報告してくださいました。患者さんの状態に応じて、ケアプランの中止や変更をする判断の大切さを学びましたね。
■気配りが患者さんの心を開く
さて、病棟実習最終日。午後2時過ぎから、大熊看護師長と中川則子看護主任を交えて最終カンファレンスが始まった。実習を通して学んだことを学生が1人ずつ発表し、師長と主任がコメントしていくという形で進められた。
R.H. 患者さんは最初、表情を表に出されませんでした。どうしたらいいか考えながら接しているうちに、「リハビリのおかげで良くなったよ」とか、車椅子を押してあげると「ありがとう」といってくださるようになりました。
大熊 Hさんが受け持った患者さんは、障害が残ることを覚悟のうえで手術を受けられましたが、それが現実となってかなりショックだったと思います。リハビリをしていく過程で感情を出せるようになったのは、Hさんのちょっとした気配りがあったからだと思います。
■患者さんが思わず本音をもらす
W.U. 患者さんがリハビリをこなされたとき、「すごいじゃないですか」といったらすごく喜んでくださいました。また頑張ろうという気持ちになっていただけて、“声がけ”もケアの一つであることを学びました。
中川 Uさんが受け持った患者さんは、意識障害があるため信頼関係を築くのが大変だったと思います。さりげない“声がけ”によってリハビリに自信を持っていただけて、私たちも喜んでいます。
K.K. 患者さんから「余命を知ってひそかに泣くときもある」と聞かされて言葉が出ませんでした。どういう気持ちで話されたのかを考え、それをどう受け止めるかによって患者さんとの関係も変わって くると思いました。
大熊 まさに、相手が学生だからこそ患者さんが本音をもらされた典型的なケースだと思います。患者さんとの距離が縮まっていい信頼関係ができましたね。
S.K. 患者さんは、少々痛くてもナースコールをされず、苦しみを自分で背負ってしまわれるタイプでした。それをどうやって引き出して楽にしてあげられるかも、看護技術だと思いました。
中川 そのような患者さんには、こちらから歩み寄っていくことが大事です。そして、“気づき”が苦痛を和らげてあげるポイントとなります。
カンファレンスを終えた後、学生たちはそれぞれ受け持った患者さんの病室を訪れ、手づくりの感謝カードを手渡した。 お互いに涙ぐむシーンも見られ、中身の濃い実習だったことを物語っていた。
2014年1月から2月にかけての約2週間、東京女子医科大学病院の病棟では、真新しい看護ユニフォームに身を包んだ初々しい女性たちがきびきびと動き回っていた。
 |
看護は、患者さんの疾病からの回復 と健康の維持・増進を図り、質の高い生活ができるよう支援する活動である。そ して、看護を支える知識や技術の基盤 となる“実践の科学”が看護学であり、それを学ぶ過程において実際に臨床の 場で行う実習は、欠くことのできない重要なものである。
女子医大看護学部では、1年生がより良い人間関係の構築を大切にした基礎看護学実習を行うのに続き、2年生と 3年生には成人看護学実習がカリキュラムに組まれ、さらに各専門領域での実習が行われる。
2年生の成人看護学実習Ⅰは、患者さんとの人間関係づくりをベースに、看護理論を用いて「根拠に基づいた看護の実践」に取り組む。3年生の成人看護学実習Ⅱでも、実習Ⅰと同様に看護計画を立案し、それを実践し評価するという一連のプロセスを4週間かけてしっかりと学ぶ。いずれも、1人の学生が1人の患者さんを受け持ちながら看護を実践していく。
女子医大病院の病棟で動き回っていた初々しい女性たちは、この成人看護学実習Ⅰを学んでいた看護学部の2年生たちである。彼女たちは少人数のグループに分かれ、中央病棟、西病棟A・B、第1病棟の各病棟に分散し、消化器外科や呼吸器外科、循環器内科、脳神経外科、化学療法緩和ケア科などの診療科を舞台に病棟実習を行った。このうち、西病棟Bの5階にある脳神経外科で学んだ5人グループの実習の様子を追ってみよう。
■ピュアな気持ちで実習に臨む
病棟実習の初日、まず脳神経外科病棟の大熊あとよ看護師長の挨拶があった。 「脳神経外科病棟に入院されているのは、 ほとんど脳腫瘍の患者さんです。中には意識障害がある患者さんもいますので、 コミュニケーションをうまく取れないことも あるでしょう。大事なことは、患者さんの表情をよく観察することです」と、脳神経外科病棟の特性を説明。
また、「患者さんは40~50歳代の人が多く、みなさんを自分の家族のように思っていろいろな話をされると思います。 その中から、患者さんの生きた情報をつかみ取ってください」 と要望。さらに、「私たちは“患者さんに選ばれる病棟づくり” をしていますが、同時に“学生に選ばれる病棟づくり”もめざしています。ですから、ピュアな気持ちで病棟実習に臨み、気がついたことはどんどん提案してください」 と語った。
このあと5人の学生はそれぞれ受け持つことになった患者さんの病室を訪れ、自己紹介。そして、患者さんの情報収集に努めた。K.K.さんが受け持った患者さんは、元気そうに見えるものの余命が短い。それを聞いたK.K.さんはショックを受け、他の4人も驚きを隠せず、命の重みを考えさせられる重々しい気分でのスタートとなった。
 |
■ケアプランを中止する判断も重要
脳神経外科病棟実習は午前8時半から始まる。前日の実習記録と当日の学習目標・看護計画を、朝のカンファレンスで教員に報告。ケアプランの修正などの指 導を受けた後、受け持つ患者さんの担当看護師と調整し、タイムスケジュールや具体的な看護方法についてアドバイスを受け、患者さんへのケアを実行する。
そして午後2時以降、その日に実施し たこと・学んだことを看護師に報告し、3時に病棟から学部校舎へ移動して学内カンファレンスを行う。こうして8日間、実習が続く。
脳神経外科病棟で実習に臨んだ5人 は、日が経つにつれて当初の重々しい気分から抜け出し、はつらつとケアに取り組むようになった。5日目朝のカンファレンスの一端を紹介しよう。
K.M. バイタルサイン (体温、血圧、脈拍、呼吸などの情報)を取りにいったら、患者さんがつらそうに眠っていました。どうしようかと考えましたが、声をおかけしてバイタルサインを取ることにしました。また、少しけいれんを起こされていましたが、それは不安な気持ちからでした。
教員 患者さんの具合が悪そうだったので、バイタルサインを取らなかったというケースがありました。素人ならそっとしておいてあげようと思うかもしれませんが、具合が悪そうだからこそバイタルサインを取らなければなりません。患者さんの状態を把握するためにバイタルサインを取ったことは適切な判断でした。患者さ んの気持ちも引き出せてよかったですね。
K.K. 患者さんは午前中から微熱があり、「首が痛い」とおっしゃったので、体温を測ることを優先させ、予定していた足浴プランの実行を中止しました。 その後、体温はさらに上昇しました。 このことから、患者さんにはそのときに必要なケアを行うことが最善の策だと思い ました。
教員 患者さんは翌日、「私の熱が上がることをKさんが予測したんですよ」 と報告してくださいました。患者さんの状態に応じて、ケアプランの中止や変更をする判断の大切さを学びましたね。
■気配りが患者さんの心を開く
さて、病棟実習最終日。午後2時過ぎから、大熊看護師長と中川則子看護主任を交えて最終カンファレンスが始まった。実習を通して学んだことを学生が1人ずつ発表し、師長と主任がコメントしていくという形で進められた。
R.H. 患者さんは最初、表情を表に出されませんでした。どうしたらいいか考えながら接しているうちに、「リハビリのおかげで良くなったよ」とか、車椅子を押してあげると「ありがとう」といってくださるようになりました。
大熊 Hさんが受け持った患者さんは、障害が残ることを覚悟のうえで手術を受けられましたが、それが現実となってかなりショックだったと思います。リハビリをしていく過程で感情を出せるようになったのは、Hさんのちょっとした気配りがあったからだと思います。
 |
■患者さんが思わず本音をもらす
W.U. 患者さんがリハビリをこなされたとき、「すごいじゃないですか」といったらすごく喜んでくださいました。また頑張ろうという気持ちになっていただけて、“声がけ”もケアの一つであることを学びました。
中川 Uさんが受け持った患者さんは、意識障害があるため信頼関係を築くのが大変だったと思います。さりげない“声がけ”によってリハビリに自信を持っていただけて、私たちも喜んでいます。
K.K. 患者さんから「余命を知ってひそかに泣くときもある」と聞かされて言葉が出ませんでした。どういう気持ちで話されたのかを考え、それをどう受け止めるかによって患者さんとの関係も変わって くると思いました。
大熊 まさに、相手が学生だからこそ患者さんが本音をもらされた典型的なケースだと思います。患者さんとの距離が縮まっていい信頼関係ができましたね。
S.K. 患者さんは、少々痛くてもナースコールをされず、苦しみを自分で背負ってしまわれるタイプでした。それをどうやって引き出して楽にしてあげられるかも、看護技術だと思いました。
中川 そのような患者さんには、こちらから歩み寄っていくことが大事です。そして、“気づき”が苦痛を和らげてあげるポイントとなります。
カンファレンスを終えた後、学生たちはそれぞれ受け持った患者さんの病室を訪れ、手づくりの感謝カードを手渡した。 お互いに涙ぐむシーンも見られ、中身の濃い実習だったことを物語っていた。
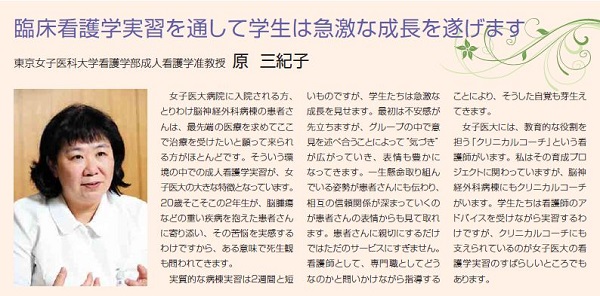 |
「Sincere(シンシア)」2号(2014年6月発行)


