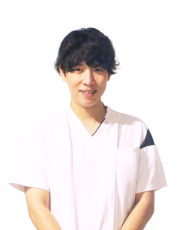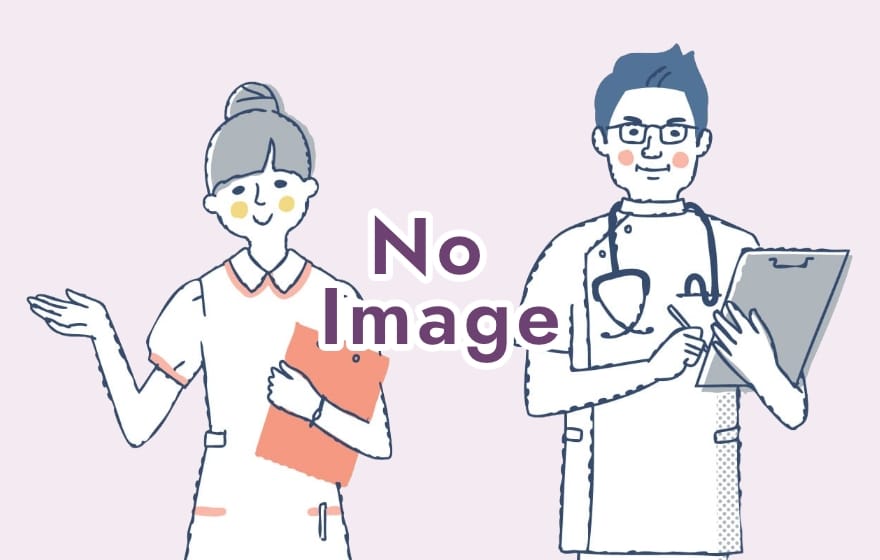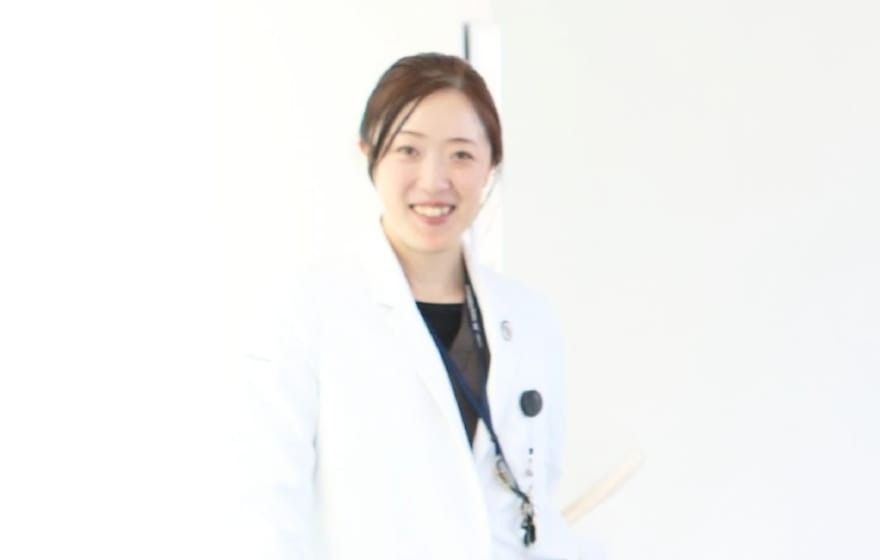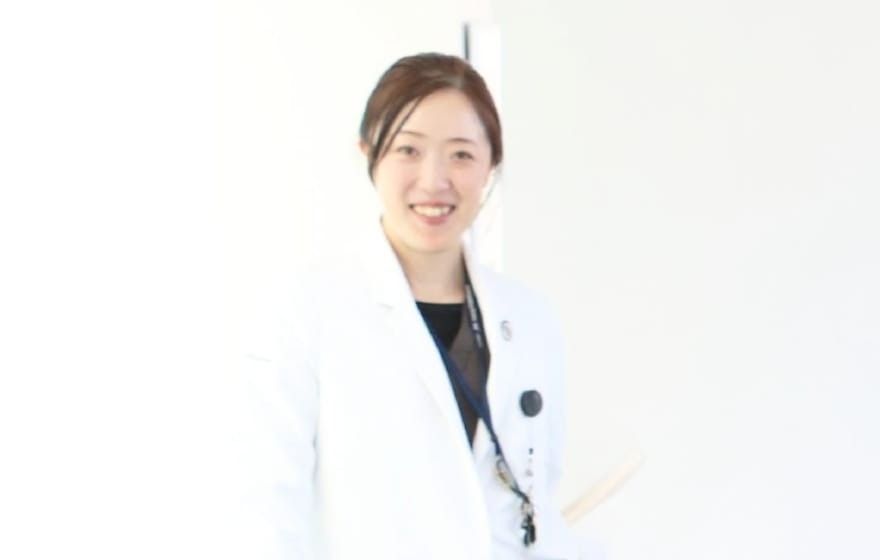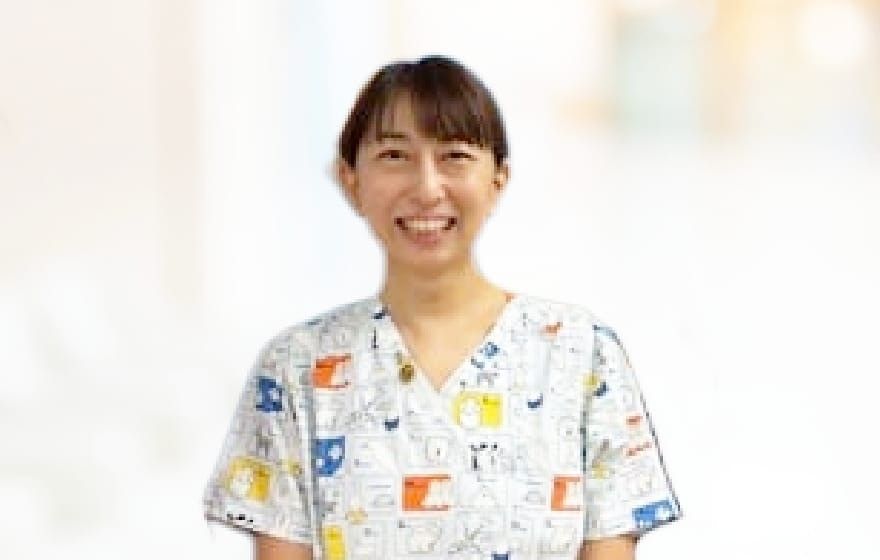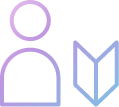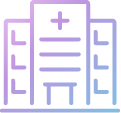スペシャリストについて
当院は、全国的にもスペシャリストの多い病院のひとつで、自分のやりたい看護を模索し、実現できる場所、自分のなりたい姿を目指せる環境を提供しています。また、一人ひとりがキャリアを重ねるなかで、自らの専門分野における知識・技術を追求し、教育や研究に取り組める環境や制度が拓かれています。
2025年現在、当院には「専門看護師:8領域22名」「認定看護師:18領域33名(うち、4名は特定行為研修修了者)」「診療看護師:9名」がいます。さらに当院には「エキスパートナース」制度があります。この制度は、臨床経験8年以上の実績のうえ、独自の専門分野を自身で決めて、本学の選考試験に合格することで「エキスパートナース」として認められるものです。たとえば、HIV/AIDS看護やVAD(補助人工心臓)看護など、7領域で7名の独自の専門分野のエキスパートナースが活躍しています。

スペシャリストの種類と役割
東京女子医科大学病院の看護部では、専門看護師・認定看護師・診療看護師・エキスパートナースが、それぞれの専門性を生かして臨床支援・教育・相談・標準化・研究に取り組み、患者さんとご家族の意思決定や療養生活を多職種とともに支えています。部署横断のチーム活動や看護専門外来と連動し、現場の学びを実践へ、実践の気づきを次の改善へとつなげる仕組みを重視しています。
Professional
専門看護師

特定の看護分野で高度な実践力を有し、患者さん・ご家族の意思決定支援や直接ケア、スタッフへのコンサルテーション・教育、調整、倫理調整、研究および研究支援を行います。部署横断で課題を捉え、看護の質向上に寄与します。
- 急性・重症患者看護専門看護師:6名
- がん看護専門看護師:4名
- 精神看護専門看護師:3名
- 小児看護専門看護師:4名
- 母性看護専門看護師:1名
- 慢性疾患看護専門看護師:2名
- 家族支援専門看護師:1名
- 在宅看護専門看護師:1名
-
慢性疾患看護
-
家族支援看護
-
急性・重症患者看護
-
精神看護
-
小児看護
-
母性看護
-
がん看護
-
在宅看護
Certified
認定看護師

特定分野の知識・技術に熟達し、臨床実践・スタッフ指導・相談対応・手順の標準化を担います。
日常のケア改善を通じて、安全で一貫性のある看護提供に貢献します。
- 救急看護認定看護師:1名
- 集中ケア認定看護師:1名
- 慢性心不全看護認定看護師:2名
- 脳卒中リハビリテーション看護認定看護師:3名
- 慢性呼吸器疾患看護認定看護師:1名
- 手術看護認定看護師:1名
- 新生児集中ケア認定看護師:2名
- 糖尿病看護認定看護師:3名
- 皮膚・排泄ケア認定看護師:3名
- 緩和ケア認定看護師:3名
- がん性疼痛看護認定看護師:2名
- 乳がん看護認定看護師:1名
- がん化学療法認定看護師:1名
- がん放射線療法認定看護師:1名
- 感染管理認定看護師:3名
- クリティカルケア認定看護師:1名
- 認知症看護認定看護師:1名
-
救急看護
-
集中ケア
-
慢性心不全看護
-
脳卒中リハビリテーション看護
-
慢性呼吸器疾患看護
-
手術看護
-
新生児集中ケア
-
糖尿病看護
-
皮膚・排泄ケア
-
緩和ケア
-
がん性疼痛看護
-
乳がん看護
-
がん化学療法看護
-
がん放射線療法看護
-
感染管理
-
クリティカルケア
-
認知症看護
Clinical
診療看護師

診療看護師は診察などを通じて、診断の補助、治療、ケアを包括的に支援し、患者満足度や医療安全の質の向上、チーム医療の推進に貢献します。医師の包括的指示のもとで高度な医学知識と臨床推論を用いて患者さんのケアとキュアを行っていきます。
- 診療看護師:9名
-
診療看護師
Expert
エキスパートナース

院内で認定された実践力と指導力を備え、症例相談、看護技術支援、勉強会運営、手順整備などを通じて現場を支えます。組織横断的に、あるいは部署に所属しながらロールモデルとなって日常ケアの質向上と人材育成に取り組みます。
日本看護協会の資格認定にはない当院オリジナルの専門領域のエキスパートナースは以下の7名です。また、専門看護師・認定看護師の資格を持つ者もその専門性をいっそう発揮して活動しています。
- HIV/AIDS看護エキスパートナース:1名
- 補助人工心臓看護エキスパートナース:1名
- エンドオブライフケアエキスパートナース:1名
- 遺伝看護エキスパートナース:1名
- 排尿ケアエキスパートナース:1名
- 食・栄養エキスパートナース:1名
- 災害看護エキスパートナース:1名
-
HIV/AIDS看護
-
補助人工心臓看護
-
エンドオブライフケア
-
遺伝看護
-
排尿ケア
-
周手術期看護
-
リエゾン精神看護
-
クリティカルケア
-
皮膚・排泄ケア
-
小児看護
-
感染管理
-
がん看護
-
がん性疼痛看護
-
がん放射線療法看護
-
糖尿病看護
-
在宅看護
-
食・栄養
-
緩和ケア
-
災害看護
Outpatient
看護専門外来のご紹介
当院の総合外来センターで力を入れている「看護専門外来」の紹介をします。当院では下記の看護専門外来を開設し、専門的な知識をもつ看護師が各診療科の医師と協働し、生活に視点をおいたQOLの向上や、疾病によるセルフケアの獲得などの指導やケアを行っています。
-
糖尿病看護外来
糖尿病看護外来のご紹介
重症化予防のためのフットケア、インスリンポンプ支援、糖尿病透析予防指導、血糖管理の支援を行っています。どの支援の場においても「患者さんの生活に合わせたセルフケア支援」を意識し、患者さんとの対話に重きをおき、大切にされていることを確認しながらセルフケアを一緒に考えていきます。対象の方 当院に通院されている糖尿病治療中の方 外来日時 平日|9:00~16:00 土曜|9:00~12:00 場所・診療科 総合外来センター3階・糖尿病代謝内科 予約方法 医師にご相談ください 料金 保険診療内 担当者 日本糖尿病療養指導士 糖尿病看護特定認定看護師 糖尿病看護認定看護師 -
排尿ケア外来
排尿ケア外来のご紹介
排尿に障害が起きると、活動や睡眠など日常生活に大きく影響します。排尿ケア外来では、快適な排尿が行えるよう一人ひとりの相談内容に応じて、排尿自立に向けた看護を行っています。専門の知識を持った看護師が、排尿にまつわる困りごとを解決し、より良い生活が送れるようサポートいたします。対象の方 排尿障害のある患者さん 尿路カテーテル管理が必要な方 外来日時 月~金|9:00~16:00 場所・診療科 外来センター3階・泌尿器科 予約方法 医師からの依頼で随時対応しています 料金 保険診療内 担当者 皮膚排泄ケア認定看護師 排尿ケアエキスパートナース -
WOC(皮膚排泄ケア)外来
WOC(皮膚排泄ケア)外来のご紹介
皮膚・排泄ケア外来では、ストーマ(人工肛門・人工膀胱)や傷、排泄のトラブルなどでお困りの方をサポートしています。 専門の看護師(WOCナース)が、装具の相談やお肌のケア、毎日の生活の工夫などを一緒に考えます。安心して笑顔で過ごせるよう、お手伝いいたします。対象の方 当院に通院されている下記の方 ・ストーマを保有している方 ・褥瘡を保有されている方 ・排泄障害がある方 外来日時 月~金|9:00~16:00 場所・診療科 外来センター1階・相談室 消化器外科・泌尿器科 予約方法 医師にご相談ください 料金 保険診療内 担当者 皮膚排泄ケア認定看護師 -
CKD(慢性腎臓病)進行予防指導外来
CKD(慢性腎臓病)進行予防指導外来のご紹介
慢性腎臓病の患者さんが少しでも長くご自身の腎臓で過ごせるよう、医師・看護師・管理栄養士が多職種チームでサポートしています。 薬剤療法、血圧、食事の管理や生活習慣の工夫などを一緒に考え、人工透析が必要となる時期をできるだけ遅らせることを目指しています。対象の方 当院に通院されている慢性腎臓病の方 外来日時 外来診療日 場所・診療科 外来センター1階・栄養指導室 外来センター3階・腎臓内科 予約方法 医師からの依頼で随時対応しています 料金 保険診療内 担当者 担当看護師(腎臓病療養指導士資格取得中) -
PD(腹膜透析)指導外来
PD(腹膜透析)指導外来のご紹介
腹膜透析を実施しながら生活していく患者さんと家族へ、腹膜透析の手技の指導や合併症予防の指導をしています。腹膜透析の患者さんが入院した際は、腹膜透析が安全に実施できるように、病棟スタッフへ腹膜透析の手技の指導や支援なども実施しています。対象の方 当院に通院されている腹膜透析患者さん 腹膜透析の指導が必要な方 外来日時 火・水・木・金 ※腎臓小児科は金のみ 場所・診療科 外来センター3階・血液浄化療法科 予約方法 医師からの依頼で随時対応しています 料金 保険診療内 担当者 腹膜透析認定指導看護師 慢性腎臓病療養指導看護師 -
腎臓移植相談外来
腎臓移植相談外来のご紹介
当院は腎臓移植においてのハイボリューム施設です。気軽に相談できるよう、レシピエント移植コーディネーター(RTC)が常勤で相談に対応しています。対象の方 腎移植希望がある方 腎提供希望がある方 腎臓移植後の方 外来日時 RCT勤務日 場所・診療科 外来センター3階・ 泌尿器科 予約方法 直通電話での予約となります 電話:03-5269-7526(移植支援室) 料金 保険診療内 担当者 レシピエント移植コーディネーター -
VAD(植込型補助人工心臓)看護外来
VAD(植込型補助人工心臓)看護外来のご紹介
これまで、100名以上の植込型補助人工心臓を装着した患者さんをフォローしてきました。今現在も60名程の患者さんを外来で支援しております。当外来ではVAD治療が必要になる可能性のある患者さん、ご家族に情報提供も行なっておりますので、お気軽にご相談ください。対象の方 当院に通院されている植込型補助人工心臓装着後の方 外来日時 毎週月・金・土|11:00~16:00 場所・診療科 外来センター2階・循環器内科、心臓血管外科、循環器小児科 予約方法 医師からの依頼で随時対応しています 料金 保健診療内 担当者 人工心臓管理技術認定士 補助人工心臓看護看護エキスパートナース -
心不全重症化予防指導外来
心不全重症化予防指導外来のご紹介
心不全の治療目的で入院した患者さんが、退院後も心不全による再入院や重症化につながらないよう、継続的に外来看護師が関わっています。体重や血圧、内服の管理、食事や運動の工夫など、療養生活で気をつけることについて患者さんやご家族と一緒に考えてサポートしています。対象の方 当院に通院されている慢性心不全で治療中の方 外来日時 外来診療日 場所・診療科 外来センター2階・循環器内科、循環器小児科 予約方法 医師からの依頼で随時対応しています 料金 保険診療内 担当者 担当看護師(心不全療養指導士) -
呼吸ケア看護外来
呼吸ケア看護外来のご紹介
COPDなどの慢性呼吸器疾患とともに生活される方を対象に息切れや日常生活での病との付き合い方などを一緒に考え、人生をより良く生きていくために、サポートをしていきます。対象の方 当院に通院されている慢性呼吸器疾患の方 外来日時 水曜日 場所・診療科 外来センター2階・呼吸器内科 予約方法 医師からの依頼で随時対応しています 料金 保険診療内 担当者 慢性呼吸器疾患看護認定看護師 3学会合同呼吸療法認定士 呼吸ケア指導士 -
がん看護外来
がん看護外来のご紹介
専門の知識と経験をもつ看護師による外来です。治療の選択や症状に伴う日常生活・療養に関する心配事、困りごと等について一緒に考え、医師と連携しながらサポートしています。対象の方 当院に通院されているがんの方 外来日時 外来診療日 場所・診療科 外来センター各診療科フロア 化学療法室・全診療科 予約方法 医師からの依頼で随時対応しています 料金 保険診療内 担当者 がんに関連した専門の知識を有する認定看護師、専門看護師 -
遺伝看護外来
遺伝看護外来のご紹介
遺伝看護外来では周産期から成人期までの患者さんやご家族を対象に遺伝学的検査、遺伝カウンセリングを提供しています。外来では認定遺伝カウンセラーの資格をもつ看護師と臨床遺伝専門医の資格を持つ医師がペアとなり、十分な時間をかけて対応して参ります。対象の方 遺伝性疾患がある方、もしくは疾患を疑われている方とそのご家族 遺伝に関する不安がある方 外来日時 水曜、金曜、土曜午前 場所・診療科 外来センター2階、3階(保険診療) 外来センター5階 特別診察室(自費診療) 予約方法 直通電話での予約となります 電話:03-5269-7509(医局)またはPHS28961(本人) 料金 保険診療、自費診療 担当者 遺伝看護エキスパートナース 認定遺伝カウンセラー -
LTFU(造血幹細胞移植後長期フォローアップ)外来
LTFU(造血幹細胞移植後長期フォローアップ)外来のご紹介
造血幹細胞移植後、移植日数を目安に免疫抑制に関する情報提供や生活指導、社会復帰やリハビリに関するご相談に対応致します。また、晩期GVHDに関する症状の早期発見や対応を行っていきます。患者さんだけでなく、ぜひご家族の方にも来ていただき移植後のフォローアップができればと思っています。対象の方 当院に通院されている造血幹細胞移植後の方 外来日時 月~金曜日(血液内科診療日に合わせて) 場所・診療科 外来センター4階・血液内科 予約方法 医師にご相談ください 料金 保健診療内 担当者 LTFU外来担当看護師(学会研修修了者) -
HIV看護外来
HIV看護外来のご紹介
HIV感染症の患者さんが、療養と折り合いをつけながらより健康で自分らしく生活を送っていただけるよう支援しています。疾患や治療、セクシュアルヘルスに関する情報をお伝えし、日常生活や精神面の困りごとなど、患者さんやご家族、パートナーの方のご相談に対応しています。対象の方 当院に通院されているHIV感染症の方 外来日時 水曜午後、金曜午前、土曜(第2・4) 場所・診療科 外来センター4階 血液内科(感染症科) 予約方法 医師にご相談ください 料金 保険診療内 担当者 日本エイズ学会認定HIV感染症指導看護師 HIV/AIDS看護エキスパートナース -
骨粗鬆症(二次性骨折予防)外来
骨粗鬆症(二次性骨折予防)外来のご紹介
日常生活動作(ADL)や手段的日常生活動作(IADL)を維持し、自立した生活を続けていくためには、骨折予防が欠かせません。そのため、骨粗鬆症について患者さんが理解を深め、食事・運動・薬物治療・転倒予防のための環境調整など、多方面から予防行動を継続できるよう支援を行っています。対象の方 当院に通院されている骨粗鬆症治療中の方 大腿骨近位部骨折手術後の方 外来日時 水・金(午前) 場所・診療科 外来センター1階・整形外科 予約方法 医師からの依頼で随時対応しています 料金 保険診療内 担当者 担当看護師(骨粗鬆症マネージャー) -
周産期関連外来
周産期関連外来のご紹介
妊娠中から産後まで皆様が心身共に健康的に過ごす事ができるよう様々な外来を設けています。情報提供や乳房のマッサージ、精神的支援など個々にあった支援を利用していただければと思います。対象の方 当院で出産予定またはご出産された方 ※母乳外来については出産施設に制約はありません 外来日時 基本|月~金 9:00~16:00 産後に関する外来|13時から曜日によって異なる マタニティークラス|毎週第3土曜日 9:00~17:00 場所・診療科 外来センター4階 母子総合医療センター またはオンライン 予約方法 予約制|緊急時には随時対応もできます 料金 公費負担、保険診療、自費診療 ※外来内容によって異なります 担当者 助産師 助産師外来
対象の方 妊娠20週以降の合併症がない妊娠経過が順調な方 外来日時 月~金 9:00~16:00 場所・診療科 総合外来センター4階・母子総合医療センター 予約方法 予約制 料金 妊婦健康診査受診票を利用した公費負担 担当者 助産師 母乳外来
対象の方 母乳や授乳スタイル、卒乳に関する相談のある女性 外来日時 月~金 13:00~16:00 場所・診療科 総合外来センター4階・母子総合医療センター 予約方法 予約制|緊急時には随時対応もできます 料金 保険診療と自費診療 担当者 助産師 2週間健診
対象の方 当院で出産した産後2週間前後の褥婦 外来日時 毎週月・水・木曜日 13:00~15:00 場所・診療科 総合外来センター4階・母子総合医療センター 予約方法 予約制 料金 自費診療 担当者 助産師 育児支援外来
対象の方 当院で出産した産後3週間前後の褥婦 外来日時 毎週月・水・木曜日 13:00~15:00 場所・診療科 総合外来センター4階・母子総合医療センター 予約方法 予約制 料金 自費診療 担当者 助産師 マタニティークラス
対象の方 当院で分娩予定の妊婦とそのパートナー、家族(1名) 外来日時 毎月第3土曜日 9:00~17:00 場所・診療科 Zoomを使用したオンライン教室 予約方法 予約制 料金 自費診療 担当者 助産師 無痛分娩意思決定支援外来
対象の方 当院で無痛分娩を検討されている妊婦とそのパートナー 外来日時 月曜~金曜 9:00~16:00 場所・診療科 総合外来センター4階・母子総合医療センター 予約方法 予約制 料金 無料 担当者 助産師