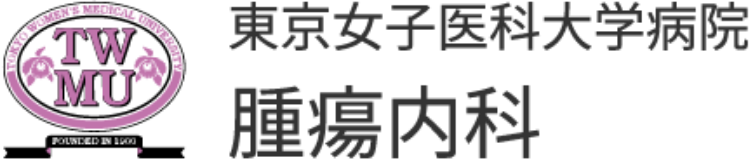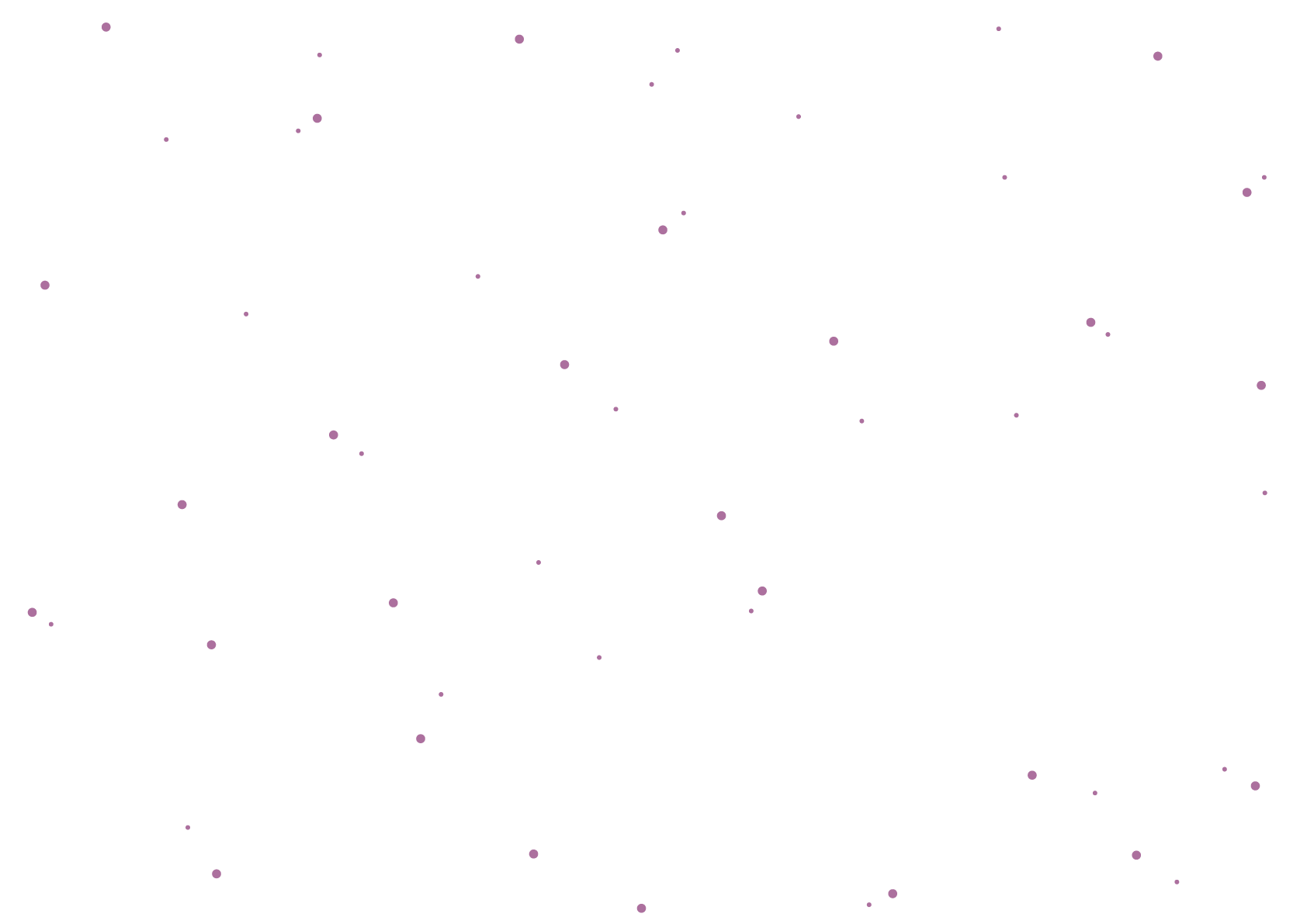News
がん治療中の「運動」と「栄養」
がん治療中の「運動」と「栄養」できることから始めてみませんか?
がん治療中の生活で、「運動してもいいの?」「どんなものを食べればいい?」「体重が増えた/減ったけど大丈夫?」といった悩みはよく聞かれます。これまでの知見に基づいて、運動・栄養・体重管理ががん治療中の患者さんの健康維持に重要です
1. 運動療法:治療中でも「動くこと」が推奨されています
海外のガイドラインでは、がん治療中でも安全に行える運動が推奨されています。特に、有酸素運動(例:ウォーキング)や筋力トレーニングは、心肺機能や筋力の向上、疲労感の軽減、生活の質(QOL)の改善に寄与することが示されています。週に150分の中強度の有酸素運動、または75分の高強度の運動が目安とされています。
また、Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC)も、運動療法の重要性を強調しており、運動が症状のコントロールや治療効果の向上、全体的な健康状態の改善に寄与することを示しています。
2. 栄養管理:食事は治療の一部です
海外のガイドラインでは、適切な栄養摂取が治療効果の最大化や副作用の軽減に重要であるとされています。特に、たんぱく質とエネルギーを重視した食事(例:魚・肉・豆類・乳製品、オイルを使った調理など)を心がけることが推奨されています。
MASCCの栄養・悪液質スタディグループも、がん患者の栄養サポートの適切な使用に関するガイドラインを策定し、食欲不振や体重減少の管理において栄養サポートの重要性を強調しています。
3. 体重管理:減少も増加も注意が必要です
治療中・治療後ともに、BMI(体格指数)を適正範囲内に維持することが望ましいとされています(一般にBMI 18.5~25)。体重減少は筋肉量の減少(サルコペニア)やがん悪液質のリスクを高め、体重増加は再発リスクの増加と関連しています。
一般的に体重管理の重要性を認識しており、運動と栄養の介入を組み合わせた多面的なアプローチが、体重の安定や筋肉量の維持、炎症の抑制など、がん患者の全体的な健康状態の改善に効果的であることを示しています。
まとめ:多職種チームによる個別対応が重要です
運動・栄養・体重管理は、がん治療の副作用軽減や生活の質の向上に寄与します。これらの介入を多職種チーム(医師、看護師、栄養士、理学療法士など)による個別対応として行うことを推奨しています。
東京女子医科大学病院・腫瘍内科では、治療中の患者さんに対し、多職種による運動・栄養サポート体制を整えています。患者さんの状態や希望に合わせたプログラムを提供しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
※この内容は、ASCOのガイドライン(Ligibel et al., J Clin Oncol. 2022;40(20):2294-2326)およびMASCCの関連ガイドラインに基づいて作成されています。