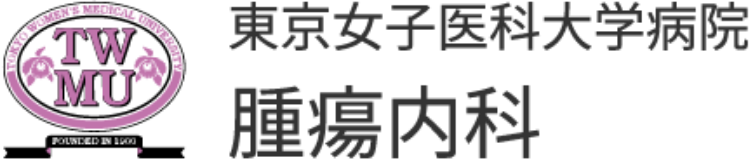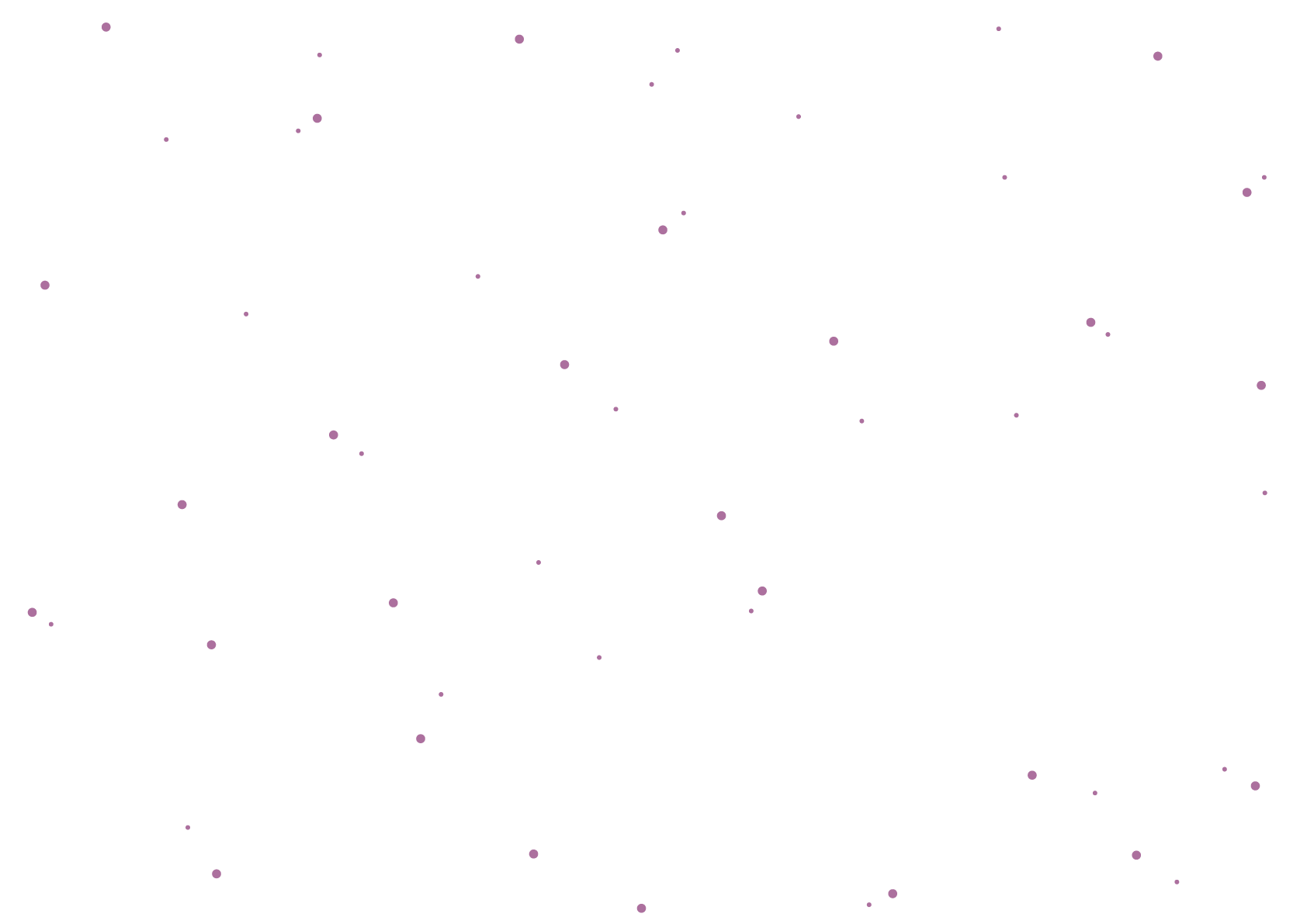News
がんとお金:医療費・高額療養費制度の使い方
がんと診断された後、治療に取り組むなかで「医療費はいくらかかるのか」「負担がどこまでになるのか」というご不安を感じる方は少なくありません。
しかし、日本には医療費の自己負担を軽減するための仕組みとして、高額療養費制度という大切な制度があります。
この制度を正しく理解し、活用することで、経済的な不安を和らげ、安心して治療に専念できる環境を整えることができます。
1. 高額療養費制度とは
高額療養費制度とは、同じ月(1日から月末まで)にかかった医療費のうち、自己負担額が所得や年齢に応じた「自己負担限度額」を超えた場合、その超えた分が後から払い戻される制度です。
- 対象となる医療費:
公的医療保険が適用される診察、検査、治療、投薬などの費用が対象です。
- 対象外となる主な費用:
入院時の食事代、差額ベッド代(個室料など)、先進医療の技術料、診断書などの文書料、保険適用外の治療費などは対象外です。
詳しくは、厚生労働省ホームページの「高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省)」をご覧ください。
2. 制度の賢い使い方:限度額適用認定証を活用しましょう
医療費が高額になることが見込まれる場合、ぜひ活用したいのが「限度額適用認定証」です。
- メリット:
この認定証を医療機関の窓口で提示すると、支払いが自己負担限度額までに抑えられます。高額な医療費を一時的に立て替える必要がなく、後日払い戻しの手続きを省けます。
- 申請方法:
ご加入の公的医療保険(協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険など)の窓口に申請します。非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。
- マイナンバーカード利用時の補足:
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、オンライン資格確認の導入と情報閲覧の同意により、事前申請が不要となる場合もあります。
申請方法の詳細は、全国健康保険協会(協会けんぽ)の案内も参考になります:
3. 知っておきたい!さらに負担を軽くする仕組み
高額療養費制度には、長期治療を支える追加的な軽減策があります。
① 世帯合算:
同じ公的医療保険に加入している家族の医療費を合算し、合算額が自己負担限度額を超える場合に対象となります。
※70歳未満の方では、1回あたりの自己負担額が21,000円以上のもののみ合算可能です。
② 多数回該当:
直近12か月以内にすでに3回以上、高額療養費の支給を受けている場合、4回目以降の自己負担限度額がさらに引き下げられます。長期間の治療を受ける方にとって大きな支援となります。
③ 高額医療・高額介護合算療養費制度:
医療保険と介護保険を併用しており、年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)の自己負担額が高額となった場合、医療費と介護費を合算して負担を軽減する制度です。
制度の全体像は、厚生労働省の以下ページが参考になります:
4. 払い戻し(還付)の手続きについて
「限度額適用認定証」を使わずに通常どおり支払った場合でも、後から申請して払い戻しを受けることができます。
- 申請先:加入している公的医療保険(協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険など)の窓口
- 提出書類:高額療養費支給申請書(保険者から送付、または取り寄せ)
- 払い戻しまでの期間:申請からおおむね3か月程度が目安です。
まとめ:安心して治療に専念するために
がんと闘う中で、医療費の不安は大きな心理的負担になりかねません。
まずはご自身が加入している保険窓口に相談し、「限度額適用認定証」の申請を検討してみましょう。
東京女子医科大学病院では、がん患者相談室が、医療費や生活に関するご相談をお受けしています。
高額療養費制度などの公的支援を賢く活用し、安心して治療に臨める環境を整えましょう。
(東京女子医科大学病院 腫瘍内科/患者さん向けコラム)