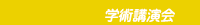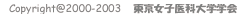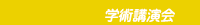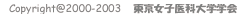|
>>プログラム
|
◆シンポジウム◆
季節性インフルエンザと新型インフルエンザ
|
1.ヒト感染メカニズムとパンデミック
八木淳二
(東京女子医科大学医学部微生物学免疫学教授)
ブタ由来の新型インフルエンザは、今年4月メキシコを発端として世界各地に感染が拡大した。その後、国内でも感染が拡がるなど社会生活に大きなインパクトを与え続けている。WHOは、今年6月12日に流行危険期フェーズをパンデミック(世界的大流行)を意味する「フェーズ6」に引き上げた。1918年3月に始まったスペインインフルエンザのパンデミック(スペインかぜ)では、世界中で約4千万人が死亡したと推定されている(致死率2%)。スペインかぜの第一波は感染性は高かったものの、致死性ではなかったとされているが、晩秋からの第二波は致死率が約10倍となり、しかも健康な若年者層がもっとも多く死に至ったことが確認されている。この事実から、今般の新型インフルエンザについても、今後さらにヒトに適応した変異によって高病原性ウイルスに変貌し、重症なインフルエンザの流行を引き起こすことが危惧される。本口演では、急速に明らかになりつつある新型インフルエンザウイルスの性状やそれらの惹起する病態について、季節性インフルエンザウイルスやスペインインフルエンザウイルスと比較しながら述べるとともに、今後のウイルスサーベイランスにおいて注視すべき変異について考えてみたい。 |
2.インフルエンザ−新型インフルエンザ(豚由来H1N1)、鳥インフルエンザ(H5N1)、スペインインフルエンザ等の病態と対策−
工藤宏一郎
(国立国際医療センター国際疾病センター長)
本年4月、メキシコ発の豚由来新型インフルエンザウイルス(S-OIV、H1N1)感染の発生が報告され瞬く間に地球規模で拡大、発生国メキシコでは多数の死亡例も報告された。 折しもアジア諸国を中心に発生している高病原性鳥インフルエンザ(H5N1)のヒトへの感染例は多くはないものの依然として報告され続け、致死率の高い本症が新型インフルエンザパンデミックに繋がるのでは、という懸念が国際的にも増大していた時であった。我々は、ベトナムと共同でヒトH5N1の疫学的特長・病態・疾患の重篤性などを分析して来た。かつ実際のH5N1患者の診療に携わり、新規治療方法や診療体制を提案し実践して来た。新型インフルエンザは既に我が国でも多くの経験をしている。その臨床像は幸いにして、殆ど軽症であり、当初懸念された事態には至っていない。一方、発生国メキシコや米国の事態は我国とやや異なる状況を示している。更に、メキシコのH1N1(S-OIV)の臨床的実情を調査する予定。(8/1現在)過去のスペイン風邪の第2波ではかなりの致死率が上昇している現象が認められているが、その理由も検証されなされなければならない。
これらのことを踏まえて、これまでの新型インフルエンザの疫学的特長や病態から、今後のインフルエンザパンデミックの臨床像を予測、今後の我が国の臨床的対応と医療体制について提言したい。
|
3.新宿区における新型インフルエンザ(豚型H1N1)対策をふりかえって
島 史子
(新宿区保健所保健予防課長)
平成21年4月下旬、メキシコ・アメリカで確認された新型インフルエンザ(A/H1N1)は、約1ヵ月半で世界規模の流行となり、日本でも国内発生から2ヵ月余で全都道府県に感染が拡大した。
検疫体制の強化から始まり、感染の封じ込め対策・拡大防止対策と矢継ぎ早な対応がなされた。この間、種々の知見の集積から今回のウイルスの病原性は低いことが判明し、強毒性を想定した新型インフルエンザ行動計画ではなく、国の運用指針での対応に切り替えられた。そして今、この秋冬以降の第2波到来やウイルスの変異が懸念される中、対策の力点は、患者の大規模な急増を抑制・緩和すること、重症患者の救命を最優先する医療提供体制の整備へと方向転換が図られている。
今回、区内の学校での集団発生事例を含め、新宿区での具体的対応の足取りを振り返り、区の組織体制、医療の確保、広報周知、関係機関との連携など、自治体レベルでの危機管理実務の1例を紹介したい。
|
4.都立墨東病院における新型インフルエンザ対策の実際
茂木玲子
(都立墨東病院看護部看護担当科長)
〔はじめに〕2009年4月メキシコで発生し世界中に拡大したインフルエンザA/H1N1(以下新型インフルエンザ)に対応すべく、第一種感染症指定医療機関である都立墨東病院では、以下の対策を進めた。
〔対策の概要〕
1.感染対策の確立と周知:発生当初は空気・飛沫・接触感染予防策をとった。その後感染経路や感染力の程度が明らかになり、飛沫感染を主とした対策に改訂した。周知は全職員に行い、説明会や防護用具使用の演習を行った。
2.三次救急、周産期救急、精神科救急で新型インフルエンザ患者発生時の対策の作成
3.病棟、外来の整備、対応職員の配置:医療物品の整備だけでなく、診療医師団や看護体制、検査体制、事務体制も組んだ。
4.新型インフルエンザ患者と他患者の振り分け:患者の来院から帰宅までの患者動線を確立し他患者との接触頻度を最小限に抑えた。また病院玄関でのトリアージ体制・発熱外来を設置し優先診療を行った。
5.報告体制の明確化:患者来院の関係部署への報告、入院決定の報告、疾患確定時の報告ルート、行政からの通達事項の伝達ルートを構築し、全職員に周知を図った。
6.有症状職員の早期発見と就業制限、職員の国内外旅行等の把握、患者と接触職員の予防投与等の検討
〔まとめ〕マニュアルは昨年度までに作成したが、実際に行動すると全部署や職員まで視野に入れていないことに気づいた。職員は委託職員も含めて考慮しなければならない。今後秋冬の流行に備え効果的で効率的な対応を目指して改訂し、訓練を行う予定である。
|